
新しく入ってきた介護職がなかなか成長しません。指導しても覚えないし、そのくせメモも取りません。利用者さんとコミュニケーションをはかるように言っても、隣でぼーっと座っているだけ。このような使えない新人を指導する気になれません。やる気がないならやめてほしいです。
このような悩みを解決していきます。
この記事の内容
- 使えないとされる新人介護職の特徴
- 新人介護職が使えなくなる理由
- 新人介護職を成長させる方法
人によって成長のスピードは違います。物覚え良く、次々と仕事を覚えることができる人もいれば、何度伝えても覚えられない人もいます。
指導する側は個人によって差があることを理解するのと、教え方に問題がないのかを常に考える必要があります。
結論を先に言うと、使えない指導者はるけれど、使えない新人はいない、ということです。
使えないとされる新人介護職の特徴
「使えない」と判断される新人の特徴は、次のものがあげられます。
- 挨拶ができない
- 言葉遣いや態度が悪い
- メモを取らない
- 同じことを何度伝えても覚えない
- 機転が利かない
- 応用が利かない
- 自ら仕事をさがすなどの積極性がない
- 質問がない
指導者はこれらの問題を解決していかなければなりません。
新人介護職が使えなくなる理由
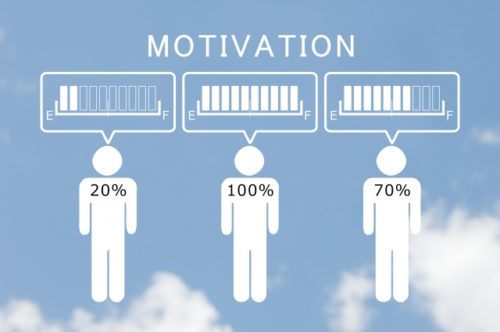
使えない新人介護職の状態から、その原因となることをあげてみます。
- 指導側が持っている当たり前で評価しているだけ
- 介護の特殊性に戸惑っている
- パーツをどう組み合わせたらいいかわからない
これらを掘り下げていきます。
指導側が持っている当たり前で評価しているだけ
使えないとされる新人介護職の特徴であげた内容について、指導者が「社会人ならばできて当たり前」と考えていないでしょうか。
そのあたり前はすべての人に通用するわけではないと、理解しなければなりません。
すでに一人前で働いているスタッフは「できて当たり前だ」と賛同するでしょう。
しかし、それは「できるようになった側」の当たり前であって、新人にとっての当たり前ではないですし、個人によっても持っている能力は異なります。
ですから「できて当たり前」のスタンスではなく、なにができて、なにができないのかをまず把握することから始めなければならないのです。
ここで重要なのは、把握することであって、評価するわけではないということです。
「あいさつは人として常識でしょう?そこに個人としての違いはないでしょう」と多くの人が考えるかもしれませんね。
それはその通りですが、ではなぜその常識ができないのでしょうか?
「できないからダメ」ではなく「できない原因はなんだろう?」と考えることが重要なのです。
あいさつをしなければならないことを理解していても、引っ込み思案であいさつをする勇気が持てないのかもしれません。
いつもタイミングを逃しているのかもしれません。
相手があいさつをさせないようなオーラを出しているのかもしれません。
評価ではなく、相手を理解しようとすれば、思考を広げることができます。
指導する側は「できるようになる」という前提を、常に持っておかなければなりません。
介護の特殊性に戸惑っている
介護の仕事は他の仕事と比べて特殊なものです。
なにも介さないで、人が直接人にサービスを提供する仕事というのは、なかなかありません。
たとえば、コンビニやスーパーなどは、商品を介して店員と客がかかわりますし、レストランでも「料理」や「食事する空間」という商品を介してかかわります。
しかも、これらの行為は生活の一部分ですが、介護の仕事は生活全般という広範囲を支える仕事になります。
そのためマニュアル化がしにくく、AのときはBという単純な労働にはならないのです。
そのような特殊性を持つ介護の仕事を理解することは、初めて経験する人にとっては難しいことです。
説明を受けたとしても、すぐに理解できる人はそれほど多くないでしょう。
ということは、混乱の中で仕事をすることになりますから、普段できて当たり前のことができなくなる、ということも起こりえるのです。
これは新人に限らず、ある程度経験を積んだ人にも起こりえることです。
部署異動で環境が変わったとたん、今まで当たり前にできていたことが、急にできなくなることがあります。
さらにできない自分に焦って、空回りした経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
環境の変化に適応することにパワーを取られてしまい、普段ならできることができなくなってしまう、ということが誰にでも起こるのです。
パーツをどう組み合わせたらいいかわからない
新人の頃は、仕事をパーツ、パーツで覚えていくことが多いと思います。
介護職の場合の流れとしては次のようになるでしょうか。
- 利用者とコミュニケーション
- 掃除や洗濯などの業務を覚える
- 利用者の名前を覚える
- 介助の技術を覚える
- ケアプランなどの見方を覚える
本当はもっと細かいですが、書ききれないのでざっくりにとどめておきます。
いずれにせよ個々で覚えていく形になりますよね。
しかし、これでは効率よく仕事を覚えるのが難しいのです。
物事は個の集まりによって成り立つのではなく「全体を形成しているのが個」であるため、全体像を先に理解できていないと、個を覚えてもつながっていきません。
ですから、なぜそれをしなければならないのか、という理解に至ることができないのです。
それがわからないと、個々の業務が単体としてでしかとらえることができず、単純に暗記するしかありません。
ただ単に暗記をしようとすることが、いかに難しいかは理解していただけると思います。
覚える目的がないと、脳に入っていかないですよね。
つまり、介護の全体像を理解してから、個々の業務を覚えていく、というやり方をしないと、成長の速度は遅くなるのです。
新人介護職を成長させる方法

新人の介護職を成長させるためには、次のことがポイントとなります。
- 目的やゴールを先に理解できるようにする
- 伝えられない指導者の問題としてとらえる
- 個別性を深める
掘り下げていきます。
目的やゴールを先に理解できるようにする
新人に仕事を教える際は、施設理念を十分に伝えるところから始めるべきです。
全体の目的が理解できないと、具体的な業務の目的が理解できないからです。
小さい頃にやった台紙がついているパズルにたとえるとわかりやすいです。
全体像というのは、新人の中にパズルの台紙を作ってあげることになります。
そして、業務の一つひとつがパズルのピースとなるわけです。
新人は、利用者とのコミュニケーションの取り方を覚えると、そのピースで自分の中の台紙を埋めていきます。
ピースが増えていくと、埋まっていないピースの絵柄も想像できるようになりますよね?
ということは、次に自分に必要なピースが分かるようになります。
どんなピースがあれば完成に近づくか、という目標ができると、解決すべき課題が自動的に生まれるので、成長のスピードは上がります。
逆に台紙がない状態だと、完成形がイメージできません。
ピースは増えていくのに、それぞれのピースのつながりが見えてこないので、常に単体で業務を覚えていくような状態になるのです。
ピースは増えたけれど、どのピースがなにを構成しているのかがわからないため、いつまで経っても一人前の仕事ができないという状態になってしまいます。
伝えられない指導者の問題としてとらえる
スタッフを「使えない」と断じてしまうと、指導者としての能力はあがらなくなります。
なぜなら、成長しない理由を相手に求めているからです。
その結果、本人のやる気がなければどうしようもない、あれでは成長しない、という結論になり、切り捨ててしまうのです。
しかし、これでは誰の成長にもなりませんし、チームにもプラスになりません。
逆に、理由を自分に向けてみたらどうでしょうか?
新人の成長が遅いのは、自分の指導の仕方に問題があるのでは?という考え方です。
人の考えや感情を変えていくのは難しいですが、自分の考えや感情はあなたの自由です。
この場合、自分にベクトルを向けると、いろいろな選択肢が生まれるはずです。
先輩スタッフに教えを乞うのも一つですし、今ならインターネットで指導の仕方を検索できます。
kindleでコーチングの本を読むのもいいでしょう。
本が苦手ならば、YouTubeの動画で勉強することもできます。
勉強したことをすぐに新人指導でアウトプットしていけば、あなたの引き出しはどんどん増えていきます。
そのひとつが新人にぴったりはまって、驚くほど成長するかもしれません。
もしそれがかなわなかったとしても、確実にあなたの能力アップにつながります。
そのほうが、新人にベクトルを向けて「使えない」と非難したり、愚痴を言うよりも、よっぽど自分やチームにとって有益な時間になります。
個別性を深める
成長のスピードや仕方は人によって違います。
「未経験、無資格の新人」とひとくくりにし、「3ヶ月以内にひとりで夜勤ができて当たり前」と設定すると、クリアできない新人はダメな人、となってしまいます。
そもそも設定した成長スピードが正しいかどうかが問題です。
これまでの成長スピードの平均値をものさしとしてはかるのでしょうが、人には個別性があります。
誰にでも当てはまるものではないということです。
スタッフの指導については抽象度を下げて、その人個人の価値観や思考の仕方などを把握していくことが必要です。
そして、それに合わせて指導を展開していかなければなりません。
会社からお金をもらって働いているのだから、教えてもらうだけでなく、もっと自分で努力するべき、という反論もあるでしょう。
しかし、お金をもらって働いているからこそ、そのお金に見合うだけの仕事が早くできるように育てなければならないのです。
そして、そのためにあなたの給料が支払われていると考えてみてください。
「忙しくてそんな暇がない」といった声も聞こえてきそうですが、頑張って先行投資することでその忙しさから解放され、さらに一人分の余裕ができるのです。
「使えないスタッフ」とレッテルを張って切り捨ててしまっては、いつまで経ってもチームは成長せず、仕事は楽にならないということになります。
まとめ
指導者側から見た「使えない新人」への対応方法について書いてみました。
結論としては「使えない新人」は「使えない指導者によって生み出される」ということになります。
指導者が新人に対して「成長できる!」という前提でかかわり、成長しない理由を指導者側の問題としてとらえれば、問題は解決するはずです。
ひとつ注意点として、新人の成長は指導者側の問題としてとらえても、自分を責めないようにしてください。
自分を責めてしまうと、新たな方法を考えることができなくなるからです。
そして、指導することが嫌になってしまいます。
また、なかなか成長しない相手に対しても、ネガティブな感情を抱いてしまいます。
新人が成長した姿をイメージし「いろいろな指導方法を試すことで、自分も成長できる」と楽しみながらかかわるようにしてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。




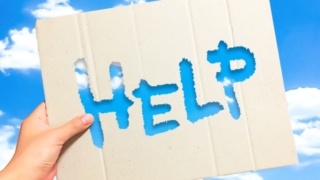





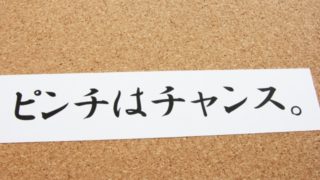





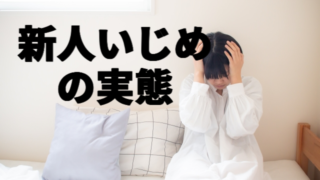




コメント