
うちの職場は人間関係が悪くて悩んでいます。リーダーの僕とは問題ないのですが、職員同士の関係が良くありません。みんなが仲良く協力し合える職場環境を作りたいです。
という悩みを解決していきます。
本記事の内容
- チームで人間関係が悪くなる理由
- チームの人間関係を改善する方法
人間関係で悩んでいる事業所は多いと思います。
職員の退職理由のトップが人間関係という数字が証明しています。
人間関係の悪化は
- 人材の流出
- スタッフ個々のパフォーマンスの悪化
をまねきます。
解決のポイントとしては、人間同士で起こる問題である、という認識です。
つまり、人間の思考パターンに焦点を当てることが、問題の根本的な解決につながります。
人間関係が悪くなる原因

人間関係が悪くなるパターンとして、次のことが考えられます。
- 自己中心的な人がいる
- 陰口が蔓延している
これらを掘り下げていきます。
自己中心的な人がいる
自己中心的な考え方の人がいると、チームとして機能しなくなることが多いですよね。
こういう人は自分が正しいと思い込んでいて、人の話しに耳を傾けないので厄介です。
その正しいも、客観的に見るとどうも間違っていることの方が多かったりします。
たとえば、利用者の負担を軽くするために、パッドを2枚重ねして夜間のおむつ交換を効率化しましょう、であったり、回数を減らすために大きめのパッドをしましょう、であったりです。
でもよく考えてみると、それは利用者の負担を減らすのではなく、介護職の負担を減らすことが目的でしょ?といったことが多いです。
経験を積んだベテランでこういう方がいると、手に負えない状況になりますね。
陰口が蔓延している
施設の雰囲気が悪くなる一番の原因は、陰口ではないでしょうか。
陰口は施設の人間関係を壊す原因になります。
なぜなら、施設全体が疑心暗鬼になって、メンバー同士の信頼が揺らいでしまうからです。
たとえばリーダーが「年末年始はどうしても人が足りなくなるので、できるだけシフト協力をお願いします」と発信したとしましょう。
それを聞いていたネガティブ思考のスタッフが、直接聞いていなかったスタッフに「リーダーが年末年始は休むなって言ってたよ。ひどいよね、あのリーダー。会社からの自分の評価しか考えてないもんね」と伝えたとしたら、どうなりますか?
聞かされた人とリーダーとの信頼関係ができていなければ、ネガティブ思考のスタッフからの話しがひとり歩きし、リーダーの信頼が著しく損なわれてしまいます。
また、陰口を言う人は、自分の意見に賛同してくれる人を囲い込もうとします。
「あなただけに言うわね」と信頼しているように装い、リーダーや施設の批判をし、まるで介護職の御意見番のような立場になったりします。
こうなると仕事が非常にやりづらくなりますね。
一方で、陰口を聞かされている人は「この人は私のこともよそで言ってるんだろうな」と思います。
このような疑心暗鬼の環境下では、職員のモチベーションは下がる一方となり、やがて退職していく人間が出てきます。
施設に致命的なダメージを与えかねません。
人間関係をよくする方法

人間関係を改善し、チームワークを良くする方法はあります。
しかし、問題のあるスタッフに直接改善を求めても効果はありません。
人間の思考パターンや本質的なところに焦点を当てる必要があります。
- 問題のある職員の自己肯定感を高める
- チームとしての目標を設定し、達成に向けて導く
- 食事会には人間関係をよくする効果がある
この3つのことを掘り下げていきます。
問題のある職員の自己肯定感を高める
自己中心的であったり、陰口を言う職員は、自己肯定感の低い人です。
自分に自信がなかったり、自分をもっと評価してもらいたいという気持ちが根底にあり、それが満たされないために裏返しの行動で表現するのです。
まとめると、自己肯定感の低い人には次の5つの特徴があります。
- 周囲に対して攻撃的
- 議論のになると、強い口調で相手を抑え込もうとする
- 実は周りの目を気にしている
- 人にはきついが、人からきつく言われると過剰に反応する
- 気分の浮き沈みが激しい
すべて該当する場合もあれば、一部かもしれません。
行動を改善してもらうためには、求めているものを満たしてあげる必要があります。
つまり、評価されている、認められているといった承認感や、重要視されているという感覚を持てるようにしてあげるのです。
具体的には、日々の仕事ぶりを承認し、本人が重要と感じる役割を任せてみることです。
外からのかかわりによって自己肯定感を高めることで、人から奪って自身を肯定する必要がなくなります。
その人の心が満たされれば、自己中心型から周囲に目を向けられるようになり、今度は与える側として他の人の心を満たしてくれます。
チームとしての目標を設定し、達成に向けて導く
職場の人間関係が悪くなる理由の一つとして、チームの目標が設定されていなかったり、絵に描いた餅になっている場合があります。
目標がないと、スタッフがパワーを向けるところがないため、その代わりに会社に対して不満を並べたり、誰かひとりをターゲットにして批判を繰り返したりして、発散しているのです。
その証拠に、ターゲットになっている人が退職していなくなっても、また新たな人がターゲットになりますよね?
また、いがみ合っていた人たちが、不満を感じる共通のことがらや人を見つけた途端、急に仲良くなったりするのを見たことがありませんか?
そうやってパワーを向けられるところを探しているのです。
そして、共通となるターゲットを見つけると、それまでいがみ合っていてもすぐに手を取り合うのです。
ということは、達成することでチームだけでなく、自分達にもメリットがあるような目標を設定し、そちらにパワーを注げるように誘導すれば、陰口や批判はなくなり、協力関係ができあがります。
食事会には人間関係を良くする効果がある
食事会をすることで、人間関係を改善できる可能性があります。
なぜなら、人は食事を共にした相手を好意的に見る性質を持っているからです。
これは人類の長い歴史の中で、食べる物がない、という餓死の恐怖と常に闘ってきたことが関係しているようです。
人は食べなければ生きていけません。
食べるということは生きていくうえで一番重要な行為です。
その結果、人間の本能により自分の命を守る=食べることが最重要視され、食の欲求を満たすことに重きを置くため「楽しいもの」とプログラムされているのです。
現在は飽食の時代として余るほど食べるものがあり、餓死するリスクはほとんどなくなりましたが、本能的な部分では変わることがないようです。
この性質を活用して、定期的に食事会を開くと問題が解決できる可能性があります。
まとめ
職場の人間関係を改善する方法について書きました。
問題が起こると、起こった内容だけを見てしまいがちですが、それでは問題を解決することはできません。
なぜなら、問題の原因はそこにないからです。
たとえば、人間は自分の満たしてほしいことを素直に表現しません。
寂しい、評価されたい、もっと認められたい、という欲求を、不満を述べることや悪態をつくこと、指示に従わない、といった行動で表現します。
まるで不良少年のようなところ誰にでもあるのです。
ですから、問題の本質をみなければ、解決しないのです。
今回の記事では、そのあたりに焦点を絞って書きました。
役に立てれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。









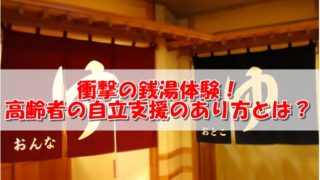











コメント