
言葉遣いに悩む介護職「介護職の言葉遣いがよく問題になります。タメ口を使う介護職が多い中で、敬語(丁寧語)で話しをするべき、という職員もいて、なかなか結論が出ません。介護職員に必要な言葉遣いとは、どういったものでしょうか?」
こんな疑問を解決します
この記事の内容
「介護職の言葉遣いの正解は何か?敬語か?タメ口か?」
どの職場でも、一度は議題にあがったことがあるかもしれません。
介護職の言葉遣いは、それほど複雑で難しい問題なのです。
あなたはタメ口派ですか?それとも敬語(丁寧語)派でしょうか。
それぞれの主張を見ながら、言葉遣いについて考えていきたいと思います。
先に結論を言うと、極論になりますが「言葉遣いはどうでもいい」となります。
なぜなら、言葉はあくまでも伝えるためのツールのひとつにすぎないからです。
要はなにを伝えるかが重要ということです。

「言葉遣いはどうでもいいって」どういうこと??

言葉遣いよりももっと大切なものがあるかもしれないね
ちなみに私は17年間介護業界にいて、6年間特別養護老人ホームの介護職をしていました。
その後、ケアマネジャー、施設長を経ていますが、利用者には介護職時代も含めて、原則として敬語(丁寧語)で話しをしています。
その上で、施設長になってからも、施設の職員とは言葉遣いについて議論を続けてきました。
その中で出てきた内容も含めて書いていきます。
介護職に求められる言葉遣いとは

介護職に求められる言葉遣いとは、どのようなものでしょうか?
言葉だけで見ると、タメ口で良い!という意見と、敬語(丁寧語)で話すのが当然!という意見に分かれます。
実際の介護職は、デイサービス以外はほとんどタメ口なのが現状ではないでしょうか?
介護職がタメ口を使うメリットと問題点
介護職はタメ口の方が良い、という人の主張は次の通りです。
「タメ口の方が良い」という意見の根拠となるのは、次のような事柄ですね。
- 施設という特殊な環境での生活
- 高齢者特有の病気や身体の変化
施設という特別な環境で、高齢者特有の病気や変化に対応するため、タメ口の方が適しているという意見になります。
では、タメ口の問題点を見ていきます。
言葉だけの問題ではないように取れるものもありますね。
言葉がきつくなりやすい、横柄に感じやすい、入所したばかりの人にもタメ口、という部分は、言葉を使う介護職の気持ちが関係しているかもしれません。
介護職が敬語(丁寧語)を使うメリットと問題点
介護職は敬語(丁寧語)で話すべきという人の主張は次の通りです。
世間で介護職の社会性が問題になることがあります。
言葉遣いも問題になる原因のひとつでしょう。
日本の文化として、目上の人には敬語で話しをしましょう、というものがありますしね。
ただ、介護職でも敬語(丁寧語)で話しができない人はほとんどいません。
職場の上司や先輩スタッフには敬語(丁寧語)で話しをしますから。
完璧な敬語が使えるか、と言われるとむずかしいかもしれませんが、それは他の業界でも同様なのではないでしょうか。
だからこそ利用者にも敬語(丁寧語)を使うべきじゃないか?ということにもなるかもしれませんけど。
では、逆に敬語で話をする問題点もあげていきます。
こちらもタメ口の問題点と同様、話す人の気持ちの問題がかかわっているようなものがありますね。
冷たく聞こえたりといったところです。
どうも、タメ口、敬語(丁寧語)のどちらかを選択すれば解決する、というわけでもなさそうです。
タメ口・丁寧語だけの問題ではない?
ここまで見てきて、タメ口・敬語(丁寧語)それぞれに良い点と悪い点があることがわかっていただけたかと思います。
もちろん、読んでいる方はどちらかの派に所属している可能性が高いので、反対の意見に対しては納得がいかないかもしれません。
しかし、客観的に見ると、介護職として理解できる部分もあるのではないでしょうか。
つまり、この問題は、言葉遣いだけに論点を置いても、解決しない問題なのでしょう。
まとめると次のようなことが言えます。
言葉の問題を考える目的は、利用者の尊厳を守ることができるかどうか、ということではないでしょうか?
ということは、やはり言葉だけで解決する問題ではない、ということになります。
なぜなら、人が相手から受ける影響は、言葉だけではないからです。
むしろ、言葉の内容による影響は非常に小さいとされています。
表情や態度、話し方、声のトーンの方がずっと影響が大きいのです。
メラビアンの法則によってそれは説かれています。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
たとえば、無表情や機嫌が悪そうな顔をしている人が丁寧に話しをしても、良い印象は受けません。
逆に、とても素敵な笑顔で、物腰の柔らかい言葉遣いで話しをされると、タメ口でも良い印象を受けるでしょう。
つまり、言葉も含めて、相手になにが伝わるかが重要ということになりますね。
介護職が使ってはいけない言葉
少し横道にそれますが、大切なことなので書いておきます。
タメ口か、敬語(丁寧語)かとは別に、介護職が使ってはいけない言葉があります。
まとめると次のようなものです。
この2つの言葉は、利用者の尊厳を損なう言葉になります。
ですから、絶対に使わないようにしてください。
時々、丁寧の度が過ぎて、赤ちゃん言葉になってしまっている人もいます。
十分注意してくださいね。
介護職に求められるのは、利用者の尊厳を守る気持ち

ここまでの内容で、言葉よりも前になにを伝えるかが重要ということがわかりました。
では伝えなければならないのは、どういったことでしょうか?
まとめると次のようになります。
- 利用者の尊厳を守り、大切に思う気持ちを表現する
- 言葉はTPOに合わせて使い分けが必要
掘り下げていきます。
利用者の尊厳を守り、大切に思う気持ちを表現する言葉かけ
繰り返しになりますが、言葉遣いの目的を考えると、言葉だけで問題は解決しません。
言葉をいくら丁寧にしても、表情や態度が丁寧でなければ意味がないからです。
では、その元になるのはなんでしょう?
それは、相手に対する気持ちではないでしょうか。
介護職には、利用者を敬い、尊厳を守ることが求められます。
ですから、その気持ちを持って、それが利用者や周囲に伝わる接し方をしなければなりません。
そして、ここで重要なのは、人の価値観はそれぞれちがうということです。
言葉はTPOに合わせて使い分けが必要
つまり、言葉遣いはタメ口もしくは敬語(丁寧語)が正解、と断定できません。
TPOに合わせた使い分けが必要なのです。
たとえば次のような要素が考えられます。
- 利用者と介護職の関係性
- 利用者の価値観
- 家族の価値観
- 利用者の心身機能の状態
- 公の場か、個人の関係の場か
誰でも彼でもタメ口を使うのは大間違いですし、逆に敬語(丁寧語)で話せば良いというわけでもありません。
砕けた関係を求める人もいれば、メリハリを求める人もいます。
認知症や耳の遠い人であれば、言葉を短く切らないと伝わりにくいでしょう。
家族の中にも、タメ口を「親しさを感じて嬉しい」と思う人もいれば、敬語(丁寧語)の方が大切にされていると感じる人もいます。
総合的に考えると、介護職としては、それらを理解、把握して、その時々に合わせて使い分けられる能力が求められる、ということではないでしょうか。
まとめ
介護職の利用者に対する言葉遣いについて書きました。
最終の結論としては、言葉はあくまでも伝えるツールのひとつであって、なにを伝えるかが言葉よりも重要ということです。
ですから、どんな言葉を使うか、という議論よりも、利用者に対してどのような気持ちを持ち、どのようにしてその気持ちを伝えるか、を議論した方が良いということになります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。















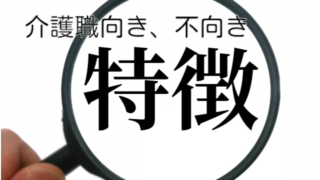






コメント