
介護職で名札を着用していますが、介護の時に邪魔になるケースが多いです。首にぶら下げていると利用者の顔に当たったりする場合があるし、どこかに引っかかったりする危険もあります。安全で邪魔にならない方法はあるでしょうか?
この悩みを解決していきます。
この記事の内容
介護職が名札を着用した方が良い理由は、以前の記事で書きました。
では、どのようにつけるのがいいでしょうか?
介護は利用者と身体を密着させる機会も多いので、意外と邪魔になることが多いですよね。
いくつかの案を書いていきます。
結論を先に書くと、名札を最優先で考えた場合、ベストは制服の胸に刺繍するか、名前の書いた布を縫いつける、もしくは貼りつける方法です。
介護職がつける名札に求められること
まず、介護職がつける名札に求められることをまとめます。
- 「名前がわかる」という本来の機能
- 利用者、職員を傷つけない安全性
- 邪魔にならない機能性
掘り下げていきます。
「名前がわかる」という本来の機能
名札の目的は周囲の人に名前がわかるようにすることですよね。
ですから、見えやすい位置になければなりません。
見えやすい位置としては、一般的に胸のあたりですね。
幼稚園児から始まって学生さんの名札はすべて、あとサービス業など、名札を付けている職種の人はほぼすべて胸のあたりですものね。
さえぎるものもありませんし、ベストでしょう。
利用者、職員を傷つけない安全性
職員の身だしなみで重要なポイントとしては「利用者を傷つけないこと」があげられます。
利用者に身体を密着させて介助することも多いですし、車椅子などに座っておられる利用者の周辺を職員が動き回ることもあるので、凶器とようなものを職員が身につけるのは避けなければなりません。
身につけるもののNGポイントをまとめます。
安全ピンの使用は万が一はずれた時に、利用者や職員を傷つけてしまうリスクが大きいのでNGです。
レストランのスタッフが良くつけているネームプレートも、硬いプラスチックなので危険ですね。
それに安全ピンか胸ポケットにはさむ金具が傷つける原因となります。
名前が印刷された紙をプラスチックケースに入れて、首からぶら下げたり、胸につけたりするタイプのものもありますが、こちらも角で傷つく恐れがありますね。
ソフトケースについても角が危ないです。
あと、名札を首から下げると、不意に車いすのハンドルに引っかかったりして、職員を傷つける恐れがあります。
また、認知症の利用者に引っ張られてしまうことも起こりえます。
邪魔にならない機能性
名前がわかっても、肝心の介助の際に邪魔になってはダメですね。
名札が利用者の顔に当たったり、介護職の動きの邪魔になったりすると、介助に支障が出て転倒などの事故につながるリスクがあるからです。
衣服にピタッとくっついて、離れるリスクのないものが理想ですね。
介護職の理想的な名札の装着方法とは?
介護職がつける名札の理想形のポイントは次の通りです。
- 名札の素材は布、もしくは糸
- 胸に縫いつけるか貼りつける
- 私服で介護している事業所での工夫
掘り下げていきます。
名札の素材は布、もしくは糸で衣服に縫いつけるか貼りつける
名札の素材は、絶対に傷つく恐れのない布、もしくは刺繍糸がベストです。
これだと身体から離れてぶらぶらすることがありませんし、傷つける恐れもありません。
もちろん介助中に邪魔になったり、気を取られたりすることもなく、安全で理想的な形であると言えます。
ただし、次のようなデメリットがあります。
制服が個人専用になってしまうのは痛いですね。
介護職は一般の仕事よりも退職率が高くなっていますから、退職するたびに制服が無駄になり、新入職があるたびに新たに作る必要が発生します。
また、ユニット型の特養やグループホームでは、家庭的な雰囲気を大切にするため、制服ではなく私服での業務となっているところがあります。
この場合、強制でつけるよう定めるには、業務時の衣服の費用を会社が負担する必要が出てくるでしょう。
やはりコストがあがることになりますね。
制服がない事業所の工夫
制服を採用していない事業所での工夫を2点紹介します
- エプロンに名札を縫いつけ、食事用とは別にして着用する
- ソフトビニールのケースに入った名札をたすきがけで着用する
- フロア、ユニットの入り口に職員の顔写真と名前を掲示する
エプロン着用はグループホームで見られますね。
私服なら名札をつけるとプライベートで使えなくなりますが、エプロンであれば問題ありません。
安ければ1枚1000円までで購入することができますし、コストも安く済みます。
もうひとつは、名札を首からぶら下げるのではなく、たすきがけにする方法です。
これであればわき腹のところに名札が来るので、介助の邪魔になるのを防ぐことができます。
ただ、たすきがけのままだと次のようなデメリットが発生します。
ここまで来ると優先順位の問題になりますね。
どこまで名札にこだわるかです。
個人的な意見としては、これなら名札を身につけることはあきらめて、ユニットやフロアの玄関に職員の顔写真と名前を掲示する形の方が良いと思います。
特にグループホームでは認知症の方を介護する施設になるので、掲示の方が適しているかもしれません。
掲示する目的はご家族に職員の名前と顔をオープンにし、信頼関係の構築と、職員自身の責任感の喚起です。
名札の目的や名前をオープンにする効果を下の記事にまとめていますので、ぜひご覧ください。
まとめ
介護職の名札の素材やつけ方について書きました。
利用者やご家族に名前を知っていただくのは、支援をするうえでとても大切なことです。
しかし、介護職の場合は仕事の内容上、名札に求められる機能がたくさんあることがわかりました。
最優先されるべきは安全であることですね。
制服にして、名前を縫いつけたり、貼りつけたりする方法がベストですが、私服を採用しているところでは使えません。
すべての事業所で制服を採用すればいいじゃないか、という意見もあるでしょうが、一方で「ユニットケアの目的である家庭的な雰囲気が制服によって崩れてしまう」という意見もあります。
双方の意見ともに、個人的には正しいと思います。
ただ、ひとつ私服の問題点を上げると、ほとんど作業着化してしまっていることですね。
利用者の汚染物を洗う際に、ハイターが付着して一部分色抜している衣服を着ているスタッフが割と多いのではないでしょうか
また、着過ぎて色あせていたり、ひどいと首回りが伸び切っていたり、破れていたりする場合もあります。
そう考えると、私服にこだわるよりも、制服化した方が利用者も気持ちよく過ごせるのではないでしょうか。
ここは事業所によって意見が分かれるかもしれませんが、あくまでも個人的な見解を述べさせていただきました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。









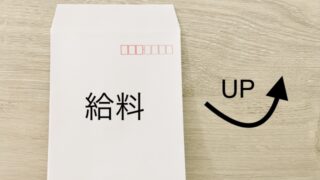












コメント